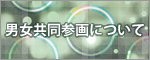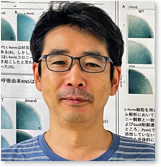
会長挨拶
日本ゲノム微生物学会 会長
大島 拓
日本ゲノム微生物学会の第7期(2024-2026)評議員会において会長に選出された大島拓です。評議員、幹事、監査の役員のみなさんのご助力をいただきながら、本学会の運営に尽力してまいります。第7期では、学会幹事や評議委員の顔ぶれが大きく変わり、より若返ったメンバー構成になりました。ゲノム解析の技術も大きく革新しており、本学会も学会創立当初の志を引き継ぎながらも、様々な面で時代に即したリニューアルを行っていきたいと思います。
ゲノム微生物学会は、かずさアカデミアホールで行われていたワークショップ「微生物ゲノム研究のフロンティア」を母体として設立されました。当時は、マイコプラズマ、シアノバクテリア、大腸菌、枯草菌、酵母等の微生物に加え、人や線虫、シロイヌナズナ、マウス等の、代表的なモデル生物の完全長ゲノム配列がサンガー法により、長い時間と人手をかけて決定され始めると同時に、得られたゲノムデータを利用したトランスクリプトーム等のポストゲノム解析がスタートしたころに重なります。ようやく手にしたゲノム配列に、我々は非常に興奮しており、それを利用した新しい研究について、いつも考えていたと思います。日本ゲノム微生物学会は、その足場として非常に重要な役割を果たしてきました。
その後、ゲノム解析は次世代シーケンス時代に突入し、解析のスピードは驚くべき速さで向上し、何年もかかっていた多様なゲノム解析が、数週間でできるようになりました。その中で、思いもしていなかった分野でも微生物ゲノム情報や微生物研究自体が活躍するようになっています。そのような新たな研究分野で、新たに微生物の研究を始めた(始めたい)研究者に方とっても、多様な分野でゲノム情報を利用し、微生物の研究を進めている研究者と情報交換ができる場は、非常に重要だと思います。そして、その様な情報交換は、既に微生物研究をされている研究者にとっても重要なものだと思います。
日本ゲノム微生物学会には、基礎から応用まで、理学・医学・工学・農学・環境学・バイオインフォマティクス等の幅広い分野の研究者が参加しています。この多様性を活かし、面白く、楽しい研究をするためのアイディアを、議論の中で見つけ出していただきたいと思います。そのためにも、日本ゲノム微生物学会は、ゲノム解析の枠にとらわれず、様々なバックグラウンド持つ微生物研究者が一堂に会して経験や知識を持ち寄り、新たな研究について議論する場の一つとなって、日本の微生物研究コミュニティーを支えたいと考えます。そのためにも、年会、ニュースレター、SNS、男女共同参画、他学会との共同シンポジウム等、様々な企画を積極的に行っていきたいと思います。3年間、よろしくお願いいたします。